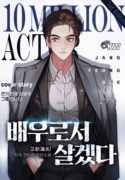Ascendence of a Bookworm: I'll Stop at Nothing to Become a Librarian RAW novel - Chapter (488)
集計中のお喋り
「ローゼマイン、報告は皆に任せるというのはどういうことだ?」
「今日は寮のほぼ全員が訓練場に来ていましたし、聞き取り調査はヴィルフリート兄様やシャルロッテの文官見習い達もしていたので、報告する内容は問題ないでしょう? わたくしは明日の準備をしたいのです」
今日の報告をする者はたくさんいるけれど、明日の集計はわたしの側近達で行うのだ。急遽お茶会室ですることになったのでテーブルや椅子の準備もしなければならないし、お茶会ではないとはいえ、領主候補生であるハンネローレも来るのだから多少のもてなしも必要だと思う。
「ダンケルフェルガーとの共同研究に関する報告として、わたくしの報告書は後日送ると養父様に連絡してくださいませ。急ぎの報告は皆にお任せいたします」
わたしは側仕え達にお茶会室のセッティングを任せ、集計方法を文官見習いとレオノーレとユーディットと共に確認し直す。
「……あ、姉上が文官仕事をしているなんて……!?」
「テオドール、動揺しすぎです。わたくしだって護衛のために神殿へ通っていたのですから、フィリーネほどではありませんけれど少しはできますよ」
失礼な、と膨れているユーディットは「フェルディナンド様が怖すぎる」と書類の提出をフィリーネやローデリヒに「ついでに持っていってくださいませ」とこっそりと頼んでいたのだが、ユーディットの姉としてのプライドの手前、テオドールに暴露するのは止めておいた。
……せっかくテオドールがユーディットを尊敬の目で見ているんだし。
「ローゼマイン様の護衛騎士は神殿で書類仕事に従事することになります。マティアスやラウレンツも春からは嫌でもすることになりますから、今回は護衛をしつつ、流れをよく見ていてくださいませ」
レオノーレの言葉にラウレンツが「文官仕事が苦手で騎士見習いになったのに」と青ざめた。ある意味、ラウレンツはアンゲリカととても気が合いそうだ。マティアスはそれほど苦手でもないようで、平然と頷いている。
「集計方法については今日のうちによく話し合ってくださいませ。姫様はこちらでハンネローレ様のお相手をしなければなりませんからね」
「でも、わたくしが主になって行う共同研究ですよ?」
わたしも文官見習いなので集計に関わるつもりだったが、リヒャルダに却下された。領主候補生であるハンネローレに事務仕事をさせるわけにもいかないし、同じように領主候補生であるわたしがいるのに、側仕えに話し相手を任せることもできないらしい。
「ローゼマイン様はハンネローレ様に本日の最後の儀式について詳しいお話を聞かなくてはならないのではございませんか? 騎士見習い達でもお教えできる歌と違って、最後の儀式はダンケルフェルガー特有のもののようですから」
競技場の中心で杖を回していたハンネローレがどのような祝詞を唱えていたのかということは、古い言葉だったせいもあってレオノーレにはよく聞き取れなかったらしい。
「ハンネローレ様はローゼマイン様と違って神殿育ちで聖典が身近というわけでもないのに、あれだけスラスラと古い言葉の祝詞が唱えられるというところが素晴らしいですね」
レオノーレの褒め言葉にわたしが深く頷いていると、リーゼレータがクスクスと笑いながら明日の話題について書かれた紙を差し出してきた。
「あれだけ分厚くて古い歴史書があるのですもの。きっとダンケルフェルガーには古い書物がたくさんあるのでしょう。その辺りも尋ねてみてはいかがでしょう? 本好きのお友達同士、きっとお話が弾むと思いますよ」
「それは素敵ですね、リーゼレータ」
集計仕事は文官に任せて領主候補生でなければできない情報収集をするように、と諭されたわたしはコクリと頷いた。
二と半の鐘が鳴るまでにお茶会室の準備は終えた。
文官達が仕事をするためのスペースは確保しているし、わたしとハンネローレが話をするためのテーブルは別に準備した。簡単につまめるように、お菓子はクッキーを準備してもらったし、側仕え達はお茶を淹れる準備もできている。
ベルの音がして来客が知らされると、わたしは出迎えるために扉の方へ向かった。グレーティアが開けてくれた扉から、ダンケルフェルガーの学生達が入って来る。もちろん、先頭はハンネローレだ。
「ごきげんよう、ローゼマイン様。本日はわざわざ場所を準備してくださってありがとう存じます」
「ごきげんよう、ハンネローレ様。こちらこそ、ダンケルフェルガーの方々に手伝っていただければ助かりますもの。御足労いただきありがとう存じます」
ブリュンヒルデの案内でハンネローレとその側近はお茶の準備されたテーブルに向かい、グレーティアの案内で共同研究に関わる文官見習い達は文官達が集まっている机へ向かう。
「ローゼマイン様、こちらをクラリッサ様から預かりました。昨日の儀式について書かれたハルトムート様宛のお手紙だそうです」
文官達を席に案内していたグレーティアが分厚い手紙を差し出してきた。
「中を確認した上でエーレンフェストに送ってくださいませ」
「かしこまりました」
別に今すぐでなくても良いのだが、上位領地であるダンケルフェルガーの学生達に緊張しているグレーティアをほんの少し息抜きでお使いに出すくらいは良いだろう。わたしが下がるように言うと、グレーティアは口元にわずかに笑みを見せた。
「では、集計の仕方を説明いたします」
フィリーネの説明する声が響き、皆が真面目に聞いている様子が見える。わたしはブリュンヒルデが淹れてくれたお茶を一口飲み、クッキーを一口食べて見せながら、文官見習い達の仕事振りを見つめる。
神殿でフェルディナンドに鍛えられたフィリーネはダンケルフェルガーの文官見習いよりよほど速く回答を捲っていく。クラリッサがフィリーネの速度に驚いているのが面白い。
「フィリーネはずいぶんと速いのですね」
「ハルトムートには全く歯が立ちませんけれど、フェルディナンド様に鍛えられた期間が長いので、書類仕事は少し得意になりました」
ふふっとフィリーネが笑うと、クラリッサは少し悔しそうな顔をした後、「わたくしもローゼマイン様の文官となる以上、負けるわけにはまいりません」と真剣な表情で集計に取り組み始めた。上位領地の上級文官としてのプライドを刺激されたのかもしれない。
「クラリッサがこうしてお仕事に集中できるのでしたら、わたくしがここに来る必要はなかったかもしれませんね」
ハンネローレがそう言って苦笑した。わたしに関する新情報があったり、共同研究のように顔を合わせる機会があったりすると、興奮してとても手が付けられないそうだ。
「……今年はその興奮具合があまりにもひどいので、もしかしたら演技かもしれないと思うこともございます」
「え?」
「神殿に入られた婚約者と別れずにいられるように、ローゼマイン様の臣下であることを強調し、他の者では手の付けられない状況を作り出しているのではないか、と」
これはきっとクラリッサの強い愛だと思うのです、と少しうっとりしているように見えるハンネローレの後ろに立っていた側仕えが軽く溜息を吐いた。
「ハンネローレ姫様、クラリッサはそこまで考えていないと思いますよ」
……うん、わたしもそう思う。クラリッサはハルトムート系。恋愛関係で結婚相手を選んでないから。
「コルドゥラはいつもこのように言うのですけれど、ローゼマイン様はどう思われますか? 寝不足になりながら婚約者への手紙を書くなんて愛がなければできないと思うのです」
そこから貴族院の恋物語の話になった。確実に婚約者の手に手紙が渡るように、婚約者の主に直接手紙を渡すことができる機会を逃さないように寝不足になりながら書いた文官の物語があったらしい。
「クラリッサの恋が成就することを、わたくし、本当に望んでいるのです」
……純粋に二人を応援するハンネローレ様が可愛いです。
クラリッサと初めて会った時に、わたしの側近目当てに候補を決めて、押し倒し武器を突きつけて求婚したいきさつを知っているので、ハルトムートとクラリッサがとても良い組み合わせだとは思うけれど、そこまで純粋な恋心があると思えない。
コルドゥラと呼ばれていた側仕えがお皿にお菓子を取り分け、お茶のお代りを淹れるとハンネローレはゆっくりとお茶を飲んだ後、話題を変えた。
「それにしても、エーレンフェストの文官見習いはとても優秀ですね。ダンケルフェルガーの文官見習いに引けを取りません」
「お褒めいただきありがとう存じます」
フィリーネだけではない。ローデリヒやレオノーレも負けていない。書類仕事に慣れていないミュリエラとユーディットは少しもたついているように見えるけれど、慣れない集計方法に戸惑っているダンケルフェルガーの文官見習い達といい勝負だ。
「あの、ローゼマイン様の護衛騎士が文官達の中に交じっているように見えるのですけれど……」
女性騎士でお茶会に同行することが多いレオノーレやユーディットの顔を覚えていたらしいハンネローレの戸惑ったような言葉にわたしは笑って頷いた。
「えぇ。神殿では護衛騎士も書類仕事をしていますから、このように人数が必要な時には手伝ってもらうのです。クラリッサは護衛のお仕事もできる文官見習いだそうですから、同じようなものと考えていただければよろしいか、と」
「武よりの文官のようなもの……。文よりの騎士ということでしょうか?」
不可解そうにハンネローレが呟いている。騎士希望者が多いとクラリッサも言っていたし、ダンケルフェルガーでは武よりの文官はいても、文よりの騎士はいないのかもしれない。わたしの側近はダームエルを筆頭に文よりの騎士が量産される環境にあるのだけれど。
「わたくし、ハンネローレ様に昨日の儀式について詳しくお伺いしたいことがございます」
「どのようなことでしょう?」
「ハンネローレ様が儀式で使われた杖をレスティラウト様は海の女神フェアフューレメーアの物とおっしゃったのですけれど、わたくし、フェアフューレメーアの神具については詳しく知らないのです。神殿にもございませんもの」
「わたくし達の間ではそう言われているだけで、確かなことは何もわからないのです。儀式の度にアウブが出すのを見て、教えられて、領主候補生は覚えるのです。シュタープを変化させる呪文も杖のものですから、本当にフェアフューレメーアの神具かどうかはわかりません」
困ったように微笑みながらハンネローレがそう言った。レスティラウトも言っていたように知らないようだ。
「ダンケルフェルガーでは神具とは知らずに変化させていたということでしょうか? ハンネローレ様が振っている時に波の音がしたので、海の女神フェアフューレメーアの神具で間違いないと思うのですけれど」
「波の音とローゼマイン様はおっしゃいましたけれど、わたくしにはそれがどのような物かよくわからないのです。ダンケルフェルガーには海がないので、海の女神の儀式とは限りませんよ」
わたしには波の音に聞こえたあの音も、ハンネローレにとっては儀式の途中で突然耳障りで変な音が聞こえ始めて驚いただけらしい。
「ハンネローレ様、儀式の時に口にする祝詞を教えていただいてもよろしいですか? 祈りの言葉がわかれば、どの神々にお祈りしている儀式なのか、わかりますから」
「えぇ」
ハンネローレが口にする祝詞で確信を持った。
「やはり海の女神に魔力奉納する儀式のようです。三本の鍵が必要な書庫に詳しい儀式の行い方が載っていました」
「そうなのですか?」
「えぇ。白い石板の資料には暑さを払う儀式だと書かれていました。けれど、昨日の様子を考えると、魔力を奉納することでその場を鎮める効果があるのですよね? 熱を冷ます儀式なのでしょうか?」
その儀式を行うことができればローエンベルクの山でリーズファルケの卵を盗っても、火山を噴火せずにいられるかもしれない。そんなことを考えているわたしの隣で、ハンネローレも「もう一度書庫に入って資料を確認したいですね」と呟いている。祝福を打ち消すだけなのか、魔力さえ奉納すれば周囲の興奮を冷ますことができるのかがハンネローレにとってはとても大事なことらしい。
「それにしても、ローゼマイン様がご存じない神具もあるのですね。祝詞で儀式の判別もできますから、神々のことは何でもご存知なのかと思いました」
「わたくしが詳しいのは聖典に載っていることだけです。神殿に祀られている最高神と五柱の大神……あとは、個人的に思い入れがある神様としては図書館にあるメスティオノーラでしょうか。そうは言っても、初代王にグルトリスハイトを授けたということしか知らないのですけれど」
眷属の神々がたくさんいるけれど、それぞれの神具や形は特に載っていない。聖典の中心は最高神と五柱の大神なのだ。
「では、今回本好きのお茶会のためにダンケルフェルガーからお持ちした本を読むと新しいことがわかるかもしれませんね」
ハンネローレは嬉しそうに微笑んでそう言った。
「今回お持ちしたのはダンケルフェルガーにある古い本なのですけれど、聖典に載せられなかった神々の零れ話が集められた本なのです。後世で勝手に付け加えられたお話かもしれませんけれど、メスティオノーラのお話もございます。神々に詳しいローゼマイン様ならば楽しめると思いますよ」
「それはとても楽しみです」
新しい本を借りるためには今借りている本を読まなければならない。やる気がぐぐんと湧いてきた。
「ローゼマイン様、集計が終わりました」
フィリーネが差し出した集計結果にさっと目を通していく。加護を得た騎士見習いは圧倒的にダンケルフェルガーが多く、ほとんどの騎士が戦い系の加護を得ているようだ。
「毎年、数人が得られていないだけ、ですか。御加護を得る儀式でダンケルフェルガーの扱いが先生方の中で別枠になっているのも納得できますね」
複数の眷属の加護を得た者や適性のない属性の加護を得た者がダンケルフェルガーにいても、それはあまり話題にされていないのである。だからこそ、今回エーレンフェストから複数の加護を得た者が出た時に注目されたのだが、他領はもっとダンケルフェルガーを調べるべきだと思う。
……調べてもディッターしか出てこないのかもしれないけど。
共同研究にもディッターが必須なのだ。他領はディッター勝負を吹っ掛けられるのを避けるために敢えて近付かないのかもしれない。
「騎士見習いはずいぶんと多くの者が眷属から御加護を得ているようですけれど、文官や側仕えはどうなのでしょう?」
わたしが独り言の気分で呟くと、ハンネローレから返事が来た。
「……武より文官や側仕えでも御加護を得ますから、その、他領よりは多いと存じます」
これはダンケルフェルガー内の状況も知りたい。文官や側仕えの内のどれだけが戦い系の加護を得ているのだろうか。
「ダンケルフェルガーの文官や側仕えの方々にも同じように聞き取り調査をしたいですね。クラリッサ、騎士見習い以外の方々からも同じように聞き取り調査をして、こちらに提出してくれますか?」
「かしこまりました」
仕事を任された、とクラリッサが喜んでいるので、ローデリヒに聞き取り調査用の紙を持って来てクラリッサに渡すように頼む。
「こうして集計結果を見ると、他領の騎士見習い達が加護を得ることは本当に少ないのですね。七割方がダンケルフェルガーですもの」
大領地で騎士見習いの人数が多いとしても、他の領地からはどんなに多くても三人くらいなので、ずいぶんと差がある。
ちなみに、エーレンフェストには戦い系の加護を得ている者は一人もいない。これは歌や踊りを覚えることに何の意味があるのかわからなかった騎士見習い達があまり真面目にしていなかったことと、わたしが祝福を与えるため自分で神々に祈りということをしなかった結果である。
……簡単に祝福を与えちゃうから、甘やかす結果になったみたい。反省、反省。
自分で加護を得られるように騎士見習い達にはもっとお祈りをさせなければならない、とダンケルフェルガーの集計結果を見て強く思った。自分の属性以外の眷属から加護を得たフィリーネを見習ってほしいものである。
「あの、ローゼマイン様。これまでの儀式では魔力の奉納をしていないようですけれど……魔力を奉納していなくても御加護を得られるのでしょうか?」
わたしのライデンシャフトの槍で大量の魔力を奉納したため、祝福が大量に降って来たのだが、ダンケルフェルガーではこれまでの儀式で祝福が降り注いだことはなく、魔力の奉納も行ってこなかったと言っていた。
「あの儀式自体が大規模なお祈りで、シュタープを変形させた槍を使っていますから、少しは奉納されているのかもしれません。得ている御加護は全て祝詞に並んでいる神々ですから」
目に見えるくらいの祝福はなくても、多少の魔力は奉納されているかもしれない。
「それに、試合前後に儀式を行うのですから、ディッターの試合に出られる回数が多い方ほど御加護を得やすいのかもしれませんね。複数の戦い系の眷属から御加護を得た騎士見習い達は試合回数も多いようです」
数字だけが並んだ集計結果だけではわかりにくいので、研究発表の時にはグラフ化すれば少しはわかりやすくなるだろうか。集計結果を見ながら、どんなグラフにするとわかりやすいのか考えていると、ハンネローレがおずおずとした感じで話を切り出してきた。
「あの、ローゼマイン様。儀式の折、シュタープで変化させる槍をライデンシャフトの槍にすれば、ダンケルフェルガーの者でもローゼマイン様が行ったように祝福が得られるのではないか、と昨夜話し合いがございました」
ハンネローレの言葉にわたしは軽く頷いた。これまでの儀式と明確な違いが出たのだ。どのようにすれば良いのか、話し合いは出るだろう。
エーレンフェスト寮での話し合いは専ら「わたしの暴走を止めるには」と「大領地から行うように言われた時に効果的に避けるには」というところに重点が置かれていたのだが、ダンケルフェルガーでは「儀式を本来の形に戻すには」という話し合いがされたらしい。
「皆様が考えたように、実際に触って神具に魔力を通し、どのような物か明確に思い浮かべれば神具の形を作ることはできます。神殿に通うわたくしの側近にはできましたから。ただ、結構魔力を使うので、上級くらいでなければ儀式の間ずっと維持できないと思います」
わたしの言葉にハンネローレだけではなく、その周囲の側近達も頷いた。ダンケルフェルガーの貴族はディッターで祝福を受けるためならば神殿にも向かえるのだろうか。ディッターに生きるダンケルフェルガーは他所の領地と基準が色々と違うようで、少し混乱する。
……でも、別にわざわざ神殿まで行ってライデンシャフトの槍にしなくても、魔力だけ奉納すれば儀式としては問題ないと思うよ。
心の中ではそう思ったけれど、敢えて口には出さない。ディッターのために神殿に向かう気があるならば、貴族に神殿へ足を運んでもらって神殿の改革をしてほしい。神殿に対する見方を変える一助となってほしい。
「奉納する魔力量によって祝福は変わるものですから、たくさんの祝福を必要とするならば、たくさんの魔力が必要です。けれど、それを一人が負担しようとするのではなく、大人数で少しずつの魔力を奉納するようにした方が良いと思います。神殿の儀式は自分のためではなく、他者のために行う祈りですから、いくら自分が魔力を負担したところで自分への祝福はないのです」
わたしの言葉にハンネローレとその側近達が目を見張った。
「では、あれだけの魔力を奉納したローゼマイン様は……」
「昨日の儀式では祝福を受けていません。騎士見習い達は動くのに困っていましたが、わたくしに何の影響もなかったのはそのせいなのです」
一人だけに魔力を負担させるのではなく、お互いに掛け合うようにするために大人数で行う儀式があるのだと思う。わたしの言葉にハンネローレが納得の表情を見せた。
「ただ、下級貴族も一緒に儀式を行う場合は気を付けてくださいね。魔力を奪われすぎて下級貴族が倒れることもございますから」
「え?」
「皆で同じ儀式を行うと魔力が流れやすくなるのです。ですから、あまりにも魔力量に差があると、少ない者には危険なのです。ダンケルフェルガーの方々は何事も実践してみるという気概のある土地柄のようですから、ご注意くださいませ」
ディッターのためならばひとまずやってみよう、というのがダンケルフェルガーだ。わたしが神事について知っていることは注意しておかなければ、ディッターどころではなくなる可能性は高い。
「おそらく、試合の前日に儀式を行うというのも、魔力回復に時間を費やすためだとか、賜った祝福に体を慣らすためだとか、何か必ず理由があるはずなのです。安易な変更は後々への歪みも大きくなります。せっかくこれまで守って来た伝統を崩さないように、慎重に調査してから儀式に臨んでみてくださいませ」
「ご忠告、ありがとう存じます。そのように注意を促しますね」
ハンネローレが笑顔で頷いた。
ダンケルフェルガー達が帰った後、わたしは多目的ホールでフィリーネ達に教えながら集計結果をグラフ化してわかりやすい資料作りに励んだ。やっぱりお話をしているよりも手を動かしていなければ研究している気分になれない。
色々なグラフで資料をいくつも作ってとても考察しやすくなった、と満足していたら、「それは何ですか?」と他の文官見習い達に食いつかれた。どうやら貴族院ではまだグラフ化した資料は作られていなかったらしい。
「ローゼマイン、それは領地対抗戦で騒ぎにならないのか?」
「三つの大領地との共同研究自体が騒ぎの元なので、大丈夫ではないでしょうか?」
何だかとても不安になって来たので、「こんな感じにグラフを使った資料で研究発表したいのですけれど……」とフェルディナンドに相談の手紙を書くことにした。