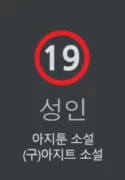Ascendence of a Bookworm: I'll Stop at Nothing to Become a Librarian RAW novel - Chapter (655)
顔色の悪い王族 その4
「父上、何をおっしゃるのですか!?」
ざわりとその場がざわめき、フェルディナンドに注目が集まる。王族は跪くトラオクヴァールとフェルディナンドを見比べ、ダンケルフェルガーのアウブ夫妻はじっとフェルディナンドを注視している。
「トラオクヴァール様。そのお言葉は、王族全員が白の塔へ入ることになったとしても、という解釈でお間違いありませんか?」
トラオクヴァールの質問に答えるのではなく、静かに問うフェルディナンドの姿に血の気の引いた顔で立ち上がったのはアナスタージウスだった。
「父上、お止めください! 貴方はツェントです。女神の化身以外の者に跪くものではありません」
「ユルゲンシュミットを治めるツェントはグルトリスハイトを持つ者でなければならぬ、アナスタージウス」
「そのグルトリスハイトはメスティオノーラの化身となったローゼマインから授けられるのです、父上。私は父上にグルトリスハイトを得て、真のツェントになっていただきたいと彼等に願いました。これまで国の行方を誰よりも案じてきた父上が最もツェントに相応しいと思っています」
立たせようとするアナスタージウスに対して、トラオクヴァールは首を横に振る。その真剣なやり取りを見ながら、わたしは感嘆の息を吐きながら隣で立っているフェルディナンドを見上げた。
……おぉ、完全にフェルディナンド様の予想通りだね。
予想されていた反応や質問が出てくるので、何というか、筋書きのあるお芝居でも見ている気分だ。真剣に言い合っているトラオクヴァールとアナスタージウスには悪いけれど、フェルディナンドにはトラオクヴァールと真面目に向き合う気などさらさらないのだ。
「トラオクヴァール様、大変失礼かと存じますが、貴方の仮定には前提条件に大きな間違いがございます。祭壇に上がれるのは全ての大神の御加護を得た者であって、グルトリスハイトを持つ者ではありません」
フェルディナンドの言葉にエグランティーヌが「そうですね」と同意を示した。エグランティーヌが口を開くとは誰も考えていなかったようで、全員の視線がそちらに向く。
「わたくしも貴族院の実技で神々の御加護を得る儀式を行った時、祭壇に上がったことがございます。シュタープを得た白い広場のようなところへ通じていたのですけれど、他には特に何もないところでした。けれど、グルトリスハイトを得ているわけではございません」
「全ての大神から御加護を得ている全属性であることが重要なのです」
わたしが言うはずだったセリフをエグランティーヌが言ってくれたので、わたしは少しだけ補足するに留めておく。
王族であるエグランティーヌに指摘されたトラオクヴァールが大きく目を見開く。わたしが言うよりも効果的だったと思う。祭壇に上がれることがメスティオノーラの書を所持している証拠にはならないのだ。
「だが、それでも、彼は……」
「えぇ。わたくし達に示してくださったグルトリスハイトへの手掛かりなどから考えると、フェルディナンド様はすでにお持ちか、もしくは、とても近いところへ到達しているのではないかと考えています」
エグランティーヌはそう言いながらフェルディナンドに視線を向ける。トラオクヴァールもフェルディナンドを見た。二人とも「グルトリスハイトを得ているのか否か」を問う顔になっている。けれど、フェルディナンドを探るようにじっと見つめているエグランティーヌと、縋るように見ているトラオクヴァールではその表情には違いがあった。
「トラオクヴァール様は本当にジギスヴァルト王子の父親ですね。とてもよく似ていらっしゃる」
跪くトラオクヴァールを見下ろすフェルディナンドはとても冷たい顔だった。「愚かで見苦しい」と実の父親に縛り上げられたジギスヴァルトとよく似ているというのが褒め言葉だと感じる者などいないだろう。その場にいた者が一斉に顔色を変えた。マグダレーナがジギスヴァルトとトラオクヴァールを見比べ、フェルディナンドを赤い瞳で軽く睨む。
「トラオクヴァール様のどの辺りがジギスヴァルト王子と似ているとおっしゃるのです?」
「ふむ。御自分に都合の悪いことは忘れ、王族という地位を笠に着て他者に自分の意を強要するジギスヴァルト王子の性根は父親譲りだと思わずにはいられませんが、マグダレーナ様の目には混沌の女神の呪いがかかっているようですね」
目が曇っていると言ってマグダレーナの言葉を切り捨てて、フェルディナンドは軽蔑を籠めた薄い金色の目でトラオクヴァールを見下ろしながら腕を組んだ。
「トラオクヴァール様がすっかりお忘れのようですから、繰り返させていただきます。私は簒奪も反逆も考えていませんし、ツェントの地位に就きたいと望んでもいません。あの時、それを内外に示すためにアーレンスバッハへ婿入りするように、と命じた貴方に私は従ったではありませんか。命懸けでアーレンスバッハに滞在した一年半が、無駄ではなかったことを祈ります」
フェルディナンドの言葉に養父様がテーブルの上に出している拳をきつく握り締めた。多分、今、養父様はトラオクヴァールを殴り飛ばしたいくらい怒っている。
「あの時はそれが最善だと判断したのだ」
トラオクヴァールの言葉に口を開いたのはフェルディナンドではなく、養父様だった。
「あの時は王命でアーレンスバッハへやるのが最善で、今度はフェルディナンドがグルトリスハイトを得ているという仮定だけで、確証さえないままに、ツェントとなって今までの王族の後始末をするのが最善だと……? いくら何でもシュラートラウムの訪れにはまだ早いのではございませんか?」
寝言は寝てから言えという意味だが、直接それをトラオクヴァールに笑顔で言える養父様は、本当にフェルディナンドの兄だなとしみじみ思う。
……それにしても、トラオクヴァール様も自分の発言を都合良く忘れる人だったのか。
フェルディナンドをこれ以上トラオクヴァールの都合で使わせる気はない養父様と、ユルゲンシュミットのためならば最善の方法を取りたいトラオクヴァールが睨み合う。火花の散りそうな雰囲気の中、柔らかな声が割って入った。
「では、フェルディナンド様はグルトリスハイトを得るわけではなく、ツェントに就くつもりはないということでよろしいでしょうか? トラオクヴァール様の申し出を受けることはないのですよね?」
エグランティーヌが頬に手を当てて首を傾げる。いつも通りのおっとりとした微笑みに見えるけれど、その明るいオレンジ色の瞳は真剣そのものだ。
「王族が白の塔へ入る代わりに神々の要求に応えるのか、アウブ・ダンケルフェルガーがグルトリスハイトを与えられてツェントとして君臨するのか……メスティオノーラの化身から示された選択肢は二つ。私がツェントになるという選択肢は最初からありませんでした。いくらトラオクヴァール様が望んだところで、選択肢が増えるわけがございません」
「お答え、ありがとう存じます。フェルディナンド様のお考えはわかりました」
王族は選択肢を与えられただけだとフェルディナンドは、トラオクヴァールの質問自体を切り捨てる。エグランティーヌは納得したように頷いたけれど、トラオクヴァールは納得できなかったようだ。大きく目を見開いて「ツェントは自力でグルトリスハイトを得た者がなるべきなのです」と訴える。けれど、その言葉はフェルディナンドから完全に黙殺された。
「あの、トラオクヴァール様」
わたしは跪いたままフェルディナンドに訴えるトラオクヴァールを見兼ねて声をかけた。
「自力でグルトリスハイトを得た者をツェントに、と望む貴方が間違っているとは思いません。メスティオノーラの書の獲得方法を広め、次代からそのように選ぶつもりです。けれど、わたくしは一旦今の王族にツェントを引き受けてほしいのです」
わたしはアドルフィーネやエグランティーヌ、マグダレーナ達を見回す。王族に嫁いで数年だったり、第三夫人として社交の場に出る機会が少なかったりした彼女達が一生白の塔で過ごす程の罪を犯しているとは思えない。
「王族の助命や連座の回避という意味もありますが、突然王族以外の者がツェントになるより、準備期間がある方が受け入れられやすいと思います。変化が大きければ大きい程、周囲からの反発も大きいですから……」
「グルトリスハイトがあれば、そのような不満を口にする貴族はおりますまい」
偽物の王だと言われ続けたトラオクヴァールだからそう思うだけだ。わたしはゆっくりと首を横に振った。
「トラオクヴァール様はグルトリスハイトを神聖視しすぎているように見受けられます。グルトリスハイトがあっても、メスティオノーラの書を得たツェントが立っても、人は不満を口にするのですよ。人々の不満に際限はありません。できるだけ軋轢が少なく、争いが少なければ良いとは思いますが、完全になくなることなどないでしょう。それは歴史が証明しています」
話している途中で強い視線を感じて、わたしはゆっくりと視線を移す。こちらをじっと見ているエグランティーヌと目が合った。
「エグランティーヌ様? どうかなさいましたか?」
わたしが呼びかけると、エグランティーヌは一度視線を下げた後、ゆっくりと顔を上げてトラオクヴァールを真っ直ぐに見た。明るいオレンジの瞳に強い光が宿っている。
「ユルゲンシュミットのためにはグルトリスハイトが必要不可欠です。ローゼマイン様がグルトリスハイトを得るならば、それを騒乱のないままに王族へもたらすためには王との養子縁組と次期ツェントであるジギスヴァルト王子との婚姻が絶対に必要だとわたくしは考えていました」
エグランティーヌにとっては、自分との結婚を機に次期ツェントから退いたアナスタージウスや、再び争いが起こることが目に見えているヒルデブラントとの結婚ではダメだったらしい。
「けれど、今回の騒動でローゼマイン様は女神の化身として王族にグルトリスハイトを与えてくださる選択肢を示してくださいました。そうであれば、ジギスヴァルト王子との婚姻も養子縁組も必要ありません。グルトリスハイトを望んだとしても、どなたにも迷惑をかけることがない状況ですけれど、トラオクヴァール様はグルトリスハイトを望まないのでしょうか?」
エグランティーヌに見つめられ、アナスタージウスが期待するようにトラオクヴァールを見つめる。妻達もトラオクヴァールを見ている。しかし、トラオクヴァールは首を横に振った。
「新たなツェントは自力でグルトリスハイトを得た者が相応しい。その考えを変えることはできぬ。新たなツェントになるべき人物は私ではない」
「そうですか。トラオクヴァール様のお考えはわかりました」
エグランティーヌはトラオクヴァールに椅子に座り直すように促した後、わたしを見た。オレンジの瞳には強い決意が宿っている。
「ローゼマイン様、わたくしが女神の化身からグルトリスハイトを得てツェントになります。ローゼマイン様にわたくしの名を捧げ、神々に宣誓いたしますから、どうかグルトリスハイトをお与えくださいませ」
「エグランティーヌ、其方……」
アナスタージウスが呆然とした顔でエグランティーヌを見つめる。エグランティーヌは「わたくし、国が乱れるのは好まないのです」とニコリと微笑んだ。
「女神の化身からグルトリスハイトを得るのは、次期ツェントだと貴族の皆様に周知されているジギスヴァルト王子が最善でした。ジギスヴァルト王子がグルトリスハイトを得ることができれば、最も長い時間をかけて緩やかに変化させることができたでしょう」
女神の化身からジギスヴァルトがグルトリスハイトを得て、古の獲得方法を実践した次代へツェントを譲れるように努力し、他の王族は廃領地のアウブとして国に尽くす。エグランティーヌにとっての最善はそれだったそうだ。けれど、不適格だと判断された。
「治世がジギスヴァルト王子に比べると長くは続かないところが少し不安ではありますが、トラオクヴァール様がグルトリスハイトを望むのであれば、今までのご苦労が報われることが喜ばしいと思いました。」
グルトリスハイトがないままに奮闘してきたのだ。トラオクヴァールがグルトリスハイトを得て正しいツェントとして国に尽くし、神々の要求に応じて国の在り方を変化させていくならば応援したとエグランティーヌは言う。けれど、トラオクヴァールは望まなかった。
「アナスタージウス様やヒルデブラント王子は全ての大神の御加護を得られていらっしゃいませんから、女神の化身と共に祭壇へ上がることができません。最初から今回のツェントとしては対象外です」
アナスタージウスとヒルデブラントが悔しそうに顔を歪める。確かに祭壇に上がれないのは致命的だ。
「ジギスヴァルト王子が御加護を得られるように、アナスタージウス様は決して抜きん出ることがないように手助けしていらっしゃいましたからね」
エグランティーヌはアナスタージウスを慰めるように微笑みながらフェルディナンドへ視線を向けた。
「そして、グルトリスハイトの有無にかかわらず、フェルディナンド様がツェントをお望みであれば、わたくしは望みませんでした。女神の化身の寵愛を受けている方と争う程無謀ではございませんし、争いは好みませんから」
……え? 寵愛? また勘違いしてる人がいるよ。
クスクスとからかうように笑うエグランティーヌに反論するべきかどうか悩んで、わたしはちらりとフェルディナンドを見た。眉間に皺を寄せて顔をしかめている。いつもと同じような仏頂面に見えるけれど、これは本気で嫌がっている顔である。ここは反論した方が良さそうだ。
「エグランティーヌ様、わたくしのフェルディナンド様への思いは家族同然に対するものであって、男女間における寵愛ではありませんし、フェルディナンド様も家族愛や政略結婚までは許容できても、そういう意味合いの寵愛を受けるのは心底嫌がっておいでなのです。そこは勘違いしないでくださいませ」
その途端、その場にいた全員がポカーンとした顔になった。皆の視線が雄弁に「何を言っているのかわからない」と告げている。
「……え?」
皆がわかっていることをわたし一人だけがわかっていないような雰囲気だ。わたしは思わず手を伸ばすと、フェルディナンドの袖をつかんだ。
「わたくしが言っていること、間違っていませんよね、フェルディナンド様!? 一緒に皆に立ち向かいましょう」
袖を何度か引っ張ると、フェルディナンドはものすごく嫌そうな顔になった。いくら面倒で嫌なことでも反論しなければ、無言は肯定だと誤解されるとわたしに教えたのはフェルディナンドだったはずだ。
「ほぅ、ローゼマインの言い分は間違っていないのか、フェルディナンド?」
「何故貴方が便乗するのでしょうか、アウブ・エーレンフェスト?」
「其方の兄として、ローゼマインの養父として、知っておくべき事柄だと思わぬか?」
「全く思いません」
ニヤニヤしている養父様を目が全く笑っていないキラキラとした笑顔でフェルディナンドが睨む。笑顔で睨むとは相変わらず器用だと思う。
「申し訳ございません。わたくし、言葉選びを間違えてしまったようです。フェルディナンド様がツェントを望むのであれば、自分が望むつもりはなかったと述べたかっただけで……」
「エグランティーヌ様のおっしゃる通り、君が脱線しすぎたのだ、ローゼマイン」
フェルディナンドはエグランティーヌに続けるように指示を出して、わたしに座り直すように軽く手を振った。確かにユルゲンシュミットを左右する大事な話し合いの場で、わざわざ反論するようなことではなかった。もしかしたら効率重視のフェルディナンドは今まで通りに勘違いさせておくことを望んでいたのかもしれない。失敗した。
「わたくしこそお話を遮ってしまって申し訳ございませんでした。続けてくださいませ」
「どなたもツェントを望まないのであれば、わたくしがなります。アウブ・エーレンフェストがおっしゃったように、王族の後始末を王族以外の方に押し付けるべきではないでしょう。それに、わたくしも子を持つ母です。できることであれば個人個人で部屋を分けられる白の塔へ入るのではなく、娘と過ごせる場があることを望みます」
……へ? 娘!? いつの間に!?
わたしは大きく目を見開いた。いつの間に妊娠して出産したのか知らないけれど、結婚した時期を考えても、エグランティーヌの娘はかなり幼いに違いない。
……エグランティーヌ様、母親になってたのか。
だったら、親が白の塔へ入れられて親子がバラバラになってしまうよりは、ツェントでもアウブでも一緒に暮らせるほうが良いと思う。
「全属性であるエグランティーヌ様の娘であれば、次代のツェントとしての素質も高いと考えられます。アナスタージウス王子にエグランティーヌ様を支えていく覚悟があれば、グルトリスハイトを与えても問題ないのではありませんか?」
わたしの言葉にアナスタージウスが警戒するように「どのような覚悟がいるのだ?」と尋ねる。そこまで心配そうな顔をしなくても、女性アウブの後継者になるのと同じようなものだ。
「エグランティーヌ様の妊娠や出産の時期に、アナスタージウス王子が代わりをできることが必須になります。アナスタージウス王子が祈りによって全ての大神から御加護を得て、エグランティーヌ様の代わりが務まるようになるまで二人目のお子を望むことはできなくなるくらいですね。回復薬をたくさん持って祠を回ればすぐですよ」
わたしが「国を支える決意をしたエグランティーヌ様のためにも頑張ってくださいませ」と激励すると、アナスタージウスはひくっと頬を引きつらせた。でも、大事な嫁と可愛い娘のためならば何でもするだろう。アナスタージウスはそういう人だ。エグランティーヌの望みは絶対に叶えるという意味で、わたしはアナスタージウスを信頼している。
「エグランティーヌ様が新しいツェントになるのであれば、王族の罪はなるべく隠す方向で動くことになります。ヒルデブラント王子もシュタープを得たことだけを隠して、そのまま過ごすことはできないでしょうか?」
わたしの言葉にマグダレーナが驚いたようにこちらを向いた。
「手枷を魔術具の腕輪のように見かけに改造して、同級生がシュタープを得る年齢まで封じておくとか……できませんか?」
「彼の側近にさせればよいが、君は相変わらず幼い者に甘すぎる」
フェルディナンドに睨まれて、わたしは少し視線を逸らす。でも、他の王族が罪を隠されて、厳しいながらも貴族として生きていくことが決まったのに、ヒルデブラントにだけ王族から領主一族になって更に厳しい罰が下るのは可哀想ではないか。
「だが、今回のヒルデブラント王子に関しては少しばかり情状酌量の余地はある。幼さ故に情報から隔離されていただろうし、ラオブルートを警戒すべきと周囲の大人が全く考えていなかった。これで周囲の大人が罪を隠されて生きていくのに、幼い者一人が目に見える大きな罪を負うのは公平だとは思えぬからな」
他人の目には見えぬ罰からは逃れられぬから良いか、と言いながらフェルディナンドがヒルデブラントの母親であるマグダレーナを見た。
「マグダレーナ様。ツェントから許可が出ているという言葉を信じて周囲の側近達まで碌に止めなかったのであれば、幼い子供が唆されても仕方ないと思われます。ですが、シュタープの性質や取得年齢が上がった理由だけでも教えていれば、ラオブルートの提案に飛び乗り、ランツェナーヴェの者達にシュタープを取らせるような愚行は防げたでしょう。第三夫人の子とはいえ王族だというのに、少々教育が疎かだったのではありませんか?」
ヒルデブラントが真っ青になり、マグダレーナが「フェルディナンド様のおっしゃる通りわたくしの教育不足でした」と目を伏せる。わたしは何度か目を瞬き、首を傾げた。
……あれ? わたし、地下書庫でヒルデブラント王子とカリキュラム変更に関するお話をしたと思うんだけど?
でも、余計なことを言ったらフェルディナンドが「説明があったのにあのような愚行を?」とか「甘やかす必要はなさそうだ」のようにヒルデブラントにもっと厳しいことを言いそうなので、余計なことは胸にしまっておいて、フェルディナンドを宥めることにする。
「大丈夫ですよ、フェルディナンド様。エグランティーヌ様がツェントになるのであれば、トラオクヴァール様がアウブになります。ヒルデブラント王子はもう王族ではなくなりますし、領主一族の教育としてはダンケルフェルガーを参考にすれば、きっとハンネローレ様のような優秀な領主候補生になれますから」
ダンケルフェルガーの領主候補生はレスティラウトもハンネローレも優秀なのだ。ダンケルフェルガー出身のマグダレーナならば、ヒルデブラントを優秀な領主候補生に育てるくらいは簡単だろう。
「あの、ローゼマイン、様は……私が次代のツェントになることを応援してくださいますか?」
ヒルデブラントが不安そうに尋ねてきた。現実的に考えると、ヒルデブラントがメスティオノーラの書を得ることはほぼ不可能だが、応援するくらいならばわたしにもできる。「もちろん応援します」と口を開こうとした瞬間、フェルディナンドに睨まれた。
「まさか女神の化身である君がこのような公の場で安請け合いをする気か? 幼子でも知っておかなければならない現実があろう」
まだ何も言っていないのに、フェルディナンドから説教された。
「おっしゃることはわかりますけれど、このような公の場で子供の夢をすっぱり切り捨てるような真似をする必要もないでしょう?」
「後で不可能を知る方が残酷ではないか」
「不可能とはどういうことですか!?」
目を見開くヒルデブラントにフェルディナンドが残酷な現実を伝える。
「ヒルデブラント王子が得たシュタープは、旧世代と同じ品質の物になります。これから祈りの重要性が周知され、シュタープを得るまでに魔力圧縮や属性を増やす努力をした同級生と共に三年時に得た場合のシュタープに比べるとかなり粗悪な物です」
あまり祈りや魔力圧縮を頑張りすぎるとシュタープの容量を超えて魔力の制御が不可能になってしまう、とフェルディナンドがヒルデブラントに告げた。
「ローゼマインは元々全属性だったので大きな祠に入れましたが、ヒルデブラント王子のシュタープは属性が欠けていて大きな祠には入れません。容量を増やすことができないことを念頭に置いて成長にも気を付けなければ、貴族として致命的な欠陥を抱えることになります。そういう苦労こそが他人の目には見えぬ、ヒルデブラント王子がこれから一生背負っていく罰です」
フェルディナンドの言葉にヒルデブラントが泣きそうな顔になった。
「つまり、私は、次代のツェントになれないのですか?」
「古代文字を勉強し、今度地下書庫の資料を読むといいですよ。当時は成人の時がシュタープの取得年齢でしたが、シュタープを得るまでに祈りを捧げ、全ての大神から御加護を得なければツェントになることはできませんでした。すでにシュタープを得ているヒルデブラント王子には不可能です」
フェルディナンドに止めを刺され、ヒルデブラントは絶望感に満ちた顔になり、ガクリと項垂れた。