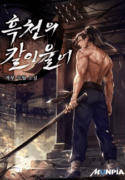Ascendence of a Bookworm: I'll Stop at Nothing to Become a Librarian RAW novel - Chapter (80)
巫女のお仕事
「これで誓いの儀式は終了だ」
「じゃあ、図書室に……」
「待ちなさい。話はまだ終わっていない」
「……はい」
神官長に促されて、わたしは祭壇前から執務机の前に移動した。フランが椅子を準備してくれたので、座る。
「ありがとう、フラン」
「……礼には及びません」
一瞬驚いたような顔をしたフランが、軽く眉を寄せた。もしかしたら、お礼を言うのもダメだったのだろうか。今度フリーダにでも貴族らしい振る舞いについて聞きに行った方がよさそうだ。
「話を始めても良いか?」
「はい、お願いします」
何の報告書か知らないけれど、神官長の机の端にはいくつもの木札や羊皮紙が積み重ねられている。神官長はそのうちのいくつかに目を通しながら、ちらりとわたしを見た。
まるで、教科書を持った教師が生徒に教えるように、話が始められる。
「君も知っての通り、神殿にいる青色神官は全て貴族出身だ。平民である君が青い衣を身につけることに良い感情を持っている者は基本的にいないと考えなさい」
「はい」
わかっていても、面と向かって言われると背筋がひやりと冷える。巫女見習いと言いだした時は、あと半年くらいの命だから、図書室の本さえ読めればそれでいいと考えていた。
けれど、神殿には魔術具があった。青の巫女見習いになることで延命が可能になり、神殿との付き合いが期間限定のものではなくなってしまった。今までのような捨て鉢ではなく、もっと色々考えなくてはならないようだ。
「今は本当に青色神官の人数が少なくて、魔力を持っている者が必要だから、無視くらいで済むだろうが、数年して、貴族が神殿に増えてくるとどうなるかはわからない。それは予め告げておく」
「……はい」
膝の上でギュッと拳を握って、唇を噛む。わたしが貴族に対して何かヘマをした場合、家族にも迷惑がかかってしまう。ここで無事に過ごせるだけの情報が欲しい。
「特に神殿長は誓いの式さえ拒む有様だ。他の青色神官も面識はないようだし、平民である君に対する感情が良いとは言えない。そのため、君の指導役は私が引き受けることになった」
身分はないのに魔力とお金だけ持っているわたしの存在は、貴族の特権意識を踏みにじるに等しいのだから、良い感情を持たれているはずがない。わかっている。けれど、貴族は良い感情を持たないと言う割には、神官長はずいぶん親身に忠告してくれていると思う。
「神官長は不快ではないんですか? その、わたしが……」
「私は優秀な人間は評価する。特に今は神官や巫女の数が減ったことで、私に執務が集中している。書類仕事が得意な君が進んで手伝ってくれるとわかっているのに、疎むわけがないだろう?」
フッと笑った腹黒笑顔に、ひくっと頬が引きつった。書類仕事が得意という発言が出たということは、前に言っていた調査が終わって、わたしに関する色々な情報が、すでに神官長には渡っているということだ。
個人情報保護なんて概念は欠片もない世界だ。貴族である神官長が聞けば、相手はベラベラ喋るだろう。一体どんな情報を握られているのだろうか。怖い。
「精一杯頑張りますけど、神殿におけるわたしの仕事って何ですか? やるべきことがあれば、教えてください」
「あぁ。君の仕事は、まず、私の助手として書類仕事だ。これが一番重要だな。午前中はここで書類仕事をしてもらう。次にお祈りと奉納。特に巫女として、お祈りはできるようになってもらわなければ困る」
「お祈りはわかりますが、奉納って何ですか?」
「神具に魔力を込めることだ。フラン、盾を」
フランが小さく頷いて、直径50~60センチくらいの盾を手に戻ってきた。金で作られているらしい円形の盾は、神具と称されるのに相応しく、複雑な文様が彫りこまれ、ところどころに青の模様がついている。
真ん中には手の平くらいの大きさで、中が燃えているようにゆらゆらと揺らめいて輝く黄色の宝石が埋め込まれている。そして、盾の周囲を縁取るようにビー玉くらいの大きさの同じような宝石がずらりと並んでいた。ただ、周囲の小さい宝石は半分ほどが黄色で、半分ほどが水晶のように透明のものだった。
「この中央の魔石に触れなさい。自分の魔力を送りこむことを思い浮かべて……」
「はい」
宝石ではなく、魔石らしい。とってもファンタジーな物にドキドキしながら、わたしが右手でそっと触れると、盾全体がぼぅっと金色に光った。それと同時に複雑な模様と見たこともない文字のような記号の羅列が薄い緑の光となって、手首ほどの位置に浮かび上がる。
うわぁ、魔法陣っぽい! すごい、すごい!
好奇心に駆られて、光る記号を見つめていると、体内の熱が掃除機で吸われていくような感触がした。身食いで死にそうだった時にフリーダが魔術具を使ってくれた時と同じ感覚だ。
せっかくなので、普段は自分の中にある魔力を閉じ込めておくための蓋を意識的に開けてみた。熱い身食いの熱がぶわっと中心から飛び出して、一気に手の平へと向かって流れていき、勢い良く吸い取られていく。
不要な熱が吸いだされていく快感に身を委ねていたわたしはハッとした。
……これは壊れないよね?
フリーダの魔術具を壊したことを思い出したわたしは、ちょっと怖くなって、思わず手を引いた。そして、少し減った魔力をまた中心に封じ込める。
魔力を放出したのは、ほんの少しの時間だったけれど、身体に負担をかける魔力が一気に減った。身体にかかっていた重石がなくなったように、身軽になった気がする。
「ふむ。小魔石7つ分か」
神官長の声に盾を見てみると、盾の周囲を飾っている小さい魔石の黄色が多くなっていた。魔力で満たされると色が変わる仕様らしい。どのくらい魔力が残っているのか一目でわかる。
……なんか、充電器になった気分。
魔力を放出していた自分の右手を握ったり閉じたりしてみる。本当に身食いの熱って魔力なんだなぁ、とか、明確な出口があったことで魔力の流れが意外とよくわかったなぁ、とか、考えていると、神官長が心配そうにわたしを覗きこんできた。
「マイン、身体に負担は?」
「えーと、何だかすっきりして、身体が軽くなった感じです」
「……そうか。負担にならない程度で奉納するように」
「わかりました」
神具に魔力を充電するのが奉納か。これは比較的楽な仕事だ。
一番大変なのは、お祈りだろう。片足立ちって、今の身体ではかなり難しい。特に、腕を横に広げてバランスを取るのではなく、斜め上に上げるところが難しい。多分、角度や耐久時間も細かく指導されるだろうし。
「それから、最後の仕事は、聖典を読んで内容を覚えることだ」
ぼそっと低く小さく付け加えられた神官長の言葉に、わたしの耳がぴぴっと反応した。読んで覚えると言いましたね? 記憶力に自信はないけど、読むだけなら任せてほしい。
「やります! すぐに図書室に行って!」
ガタッと立ち上がって、バッと手を挙げて、わたしが神官長にやる気をアピールしてみた。しかし、神官長はこちらを見ることなく、別の紙を手にとって目を通し始める。
「その前に寄付金の話に移りたい。座りなさい」
「……はい」
お金の話は大事だ。特にわたしが払うと宣言した寄付金は高額なので、わたしも寄付金のことは気になっていた。主に払い方とか、寄付金の行方とか。
「君は大金貨1枚を寄付すると言ったが……」
神官長に軽く睨まれて、わたしはベンノに相談したことを思い出す。
たしか、「一年に何度もある儀式の度に、商業ギルドとしてのお布施が集金されるが、個人的にはしたことがない」と言われた。あと、「金額が多すぎるので、悪目立ちする可能性が高い。分けて払った方がいいんじゃないか? 金使いの荒い能無しに大金を与えすぎたら周りが迷惑するぞ」とも言われた。
「えーと、払えと言われたら、払えますけど、毎月小金貨1枚ずつ支払うような分割払いってできますか?」
「寄付金はこちらが指定するものではないから、できないわけではないが、その理由は?」
「いきなり全額払ったら、大金に目が眩んで、余計な出費が増える人もいる可能性があると知人に言われまして……。神殿の財政を仕切っている人に寄付金の行方や使い方を聞いたうえで、払い方を決めた方が良いんじゃないかと思ったんです」
さすがに、ベンノの言ったままは言えない。濁した言葉でも意図は伝わったようで、神官長はわたしの言葉を聞いた後、しばらく考え込んで息を吐いた。
「寄付金は5割が神殿の維持費として使われ、残りは青色神官に分配される。神官に配られる金額には、地位によって多少の差がある。財政を預かる者の意見としては、最初は小金貨5枚で、残りを毎月小金貨一枚にした方が良い」
「その金額は何故ですか?」
わたしが首を傾げると、神殿長はまとまった羊皮紙の束をわたしの前に差し出してきた。目を通してみると、それは帳簿の一部だった。ぎょっとするわたしに神官長は書類を指差した。
「神殿の収入は大まかに分けて、領主から与えられる奉納金と儀式の際のお布施、それから、青色神官の実家が負担する支援金がある。つまり、青色神官の減少は収入の減少に直結する。商人に分かりやすく言うなら、今の神殿は赤字経営だ。それから、神殿長は搾りとれと叫んでいたので、機嫌を取るためにもまとまった金額があると助かる」
ずいぶん内情をぶっちゃけられた気がするけれど、神殿が赤字経営なんて、わたしが聞いても良い内容だったんだろうか。
「えーと、神官長。それって、わたしに言っちゃって良い内容なんですか?」
「数日後には君が携わる仕事になるから、今教えたところで問題なかろう」
書類の手伝いというのは、オットーのところでやった計算だけを手伝わされるわけではなく、かなり突っ込んだことまでやらされるらしい。
「……わかりました。お金はどうやって渡したらいいですか? 大金はいつもギルドカードでやりとりしているんですけど、神官長はギルドカードなんて持ってませんよね?」
「君が持ってくればいいだけだろう?」
神官長は簡単にそう言ってくれるが、わたしの場合、大金はカードでのやり取りばかりで、自分の手では金貨を持ったことがない。わたしみたいな子供が大金を持って、商業ギルドから神殿まで歩くなんて怖すぎる。
冬の手仕事の時の手数料でさえ、マルクに運ぶのを手伝ってもらうくらい小心者なのだ、わたしは。
「大金に慣れている神官長には簡単な事でも、わたしが持ち運ぶには、大金すぎて怖いですよ」
「ハァ、一体何のための側仕えだと思っている?」
はい? 側仕え?
神殿長の言葉に思わず背後に並んで控えている側仕えを見回して、わたしは首を傾げた。あの人選ミスな側仕えに大金を預けるなんて、できるわけがない。
フランならまだ神官長の命令なら何とか聞いてくれるかもしれないが、デリアやギルは嫌がらせに使われそうで怖い。わたしに対する態度を見た限りでは、どの側仕えもまだ信用できない。
「他の人を挟んで、もし、渡した、もらってないって話になったら嫌じゃないですか。小金貨5枚なんて、預けるのも預かるのも怖いですよ」
「……君は側仕えを信用していないのか?」
不思議そうな顔で神官長に言われて、わたしも不思議な気分になった。貴族というのは、初対面の態度の良くない他人を信用して、小金貨5枚が渡せるのだろうか。それとも、何か裏切らないような契約魔術のような物を結んでいるのだろうか。
わたしが側仕えを紹介されたところを思い返してみるが、それらしい契約はなかったはずだ。魔術に関する契約は血を使うので、さすがにわたしでもわかる。
「側仕えって言っても、何の強制力もない、初対面の他人ですよね? いきなり大金を預けるほど信用なんてできませんよ、普通」
それも、友好的な態度が欠片もない相手だよ? 無理、無理。ここの側仕えに比べたら、まだギルド長の方が信用できるって。
わたしがお金に関して信用できる大人は限られている。ベンノかマルクについて来てもらうことはできるだろうか。神官長は貴族なので、繋がりができることを考えれば、ベンノも断りはしないだろう。断らないでくれたら嬉しい。
「大金持つのに慣れていて、わたしが信用できる大人について来てもらいたいので、神殿にその人をいれる許可を頂けませんか?」
「それは誰だ?」
「商業上のわたしの後見役をしてくださっているギルベルタ商会のベンノさんです」
「……ふむ、いいだろう」
ルッツが迎えに来てくれたら、一度お店によって相談しよう。ついでに、側仕えの使い方も知らないか聞いてみたい。従業員の使い方と共通するところはないだろうか。
考え込むわたしの前で、神官長は帳簿を閉じて、アルノーに渡した。
「今日、話しておくことは以上だ。マイン、何か質問は?」
「はい! 4の鐘の後、ルッツが迎えに来るまで図書室で本を読みたいのですが、わたし、図書室に入れますか? ぜひ、聖典を読んで覚える仕事がしたいです!」
「ルッツと言うと、君の体調管理をしている少年だったな。これからは、側仕えに体調管理をさせるように」
図書室に入れるかどうか聞いているのに、体調管理の話になってしまった。
わたしはもう一度側仕えを見る。ガシガシと頭を掻いていて明らかにやる気のなさそうなギルと、ぼーっと窓の外を見ているデリアと、わたしを通り越して神官長を見ているフラン。どう考えても、わたしの体調管理ができるようになるとは思えない。
「側仕えが管理できるようになるまでは、ルッツを同行するように家族に言われてるんです。ルッツにも負担が大きいですから、早くできるようになって欲しいとわたしも思ってますよ。頑張ってくれたらいいですね。……それで、図書室に行っても良いですか?」
「あぁ。フラン、案内してやれ」
「かしこまりました」
神官長の言葉に軽く手を交差させて、フランが微かに笑みを浮かべて頷く。誇らしげな顔つきはわたしが見ていたものとは全く違うもので、フランの主が誰であるかを如実に示していた。
まぁ、でも、神官長付きの灰色神官だったら、まだ安全だろう。神官長に心酔してそうだし、問題行動を起こすことはなさそうだ。そんな評価を下しながら、わたしはフランの後ろを飛び跳ねるようにして歩く。
何はともあれ、図書室~! これはお仕事なの! わたしのお仕事!
浮かれて足取り軽く歩くわたしの後ろから、デリアとギルが付いてきていた。神官長の部屋から少し離れたところで、ギルがケッと悪態を吐いた。
「図書室なんかに行きたがるなんて、バカじゃねぇの」
カチーン! 本の偉大さも知らないバカはお前だ!
くるりと振り返って、わたしが力一杯ギルを睨むと、ギルは鼻の頭に皺を刻んで臨戦態勢に入った。
「何だよ、その目。お前なんか貴族でも何でもないただの平民だろ? オレ達と大して変わらないのに青の衣なんて着て偉そうにしやがって。俺はお前なんか主とは思わないからな。絶対に命令なんて従わねぇし、目一杯困らせてやるからな」
ギルがわたしを主と思わないのと同じように、わたしもギルを側仕えだとは思えないし、今のわたしには躾のなってないガキを躾けるだけの体力も気力も愛情もないのだ。故に、流す。
「そう、わかった。お互い様だね」
「……っ!? わかったって何だよ!? バカにしてんのか!?」
ガーッと怒鳴り始めたギルに背を向けて、わたしは歩き始める。
その途端、背後から少女の高い声が響いた。
「本当にバカにしてるわよね」
「デリア?」
表面上の笑顔さえも消し去って、デリアはフンと鼻を鳴らす。男に媚びるタイプだと思っていたので、他の側仕えがいる間は本性を出さないだろうと思っていたのに、あっさり出したことにビックリした。
どうやら、デリアへの評価を変えなければいけないようだ。もしかしたら、男に媚びる八方美人タイプではなかったのかもしれない。それとも、狙った相手以外には媚びない肉食系ハンタータイプ?
わたしがデリアを見つめていると、深紅の髪をバサッと掻き上げて、高慢な少女漫画のキャラクターのようにツンと顎を上げた。8歳という幼さで、それなりに様になっているところが怖い。
「あぁ、もー! せっかく神殿長付きの見習いになれたのに、よりによって、あたしの魅力が通じない女に回されるなんて。しかも、鈍臭そうな貧民の子供なんでしょ? ホント最悪よね」
デリアは神殿長の回し者らしい。友好的ではないわけだ。
それにしても、一体何を考えてスパイ宣言してるんだろう? これも神殿長の指示?
「じゃあ、交代してもらうね」
いきなりの暴露に首を傾げてつつ、これ幸いと交代を申し出たら、デリアはやや吊り気味の目を更に吊り上げて、怒りだした。
「もー! あんた、ホントにバカね。交代なんてしないわよ。何言ってんの!?」
それはこっちのセリフ。何言ってんの?
「神殿長から直々にあんたを困らせるように頼まれたのよ? 交代なんてことになったら、あたしの能力が疑われるでしょ!」
言葉は通じるのに、お互い話が通じないようだ。全く理解できない。神殿長から直々に嫌がらせを頼まれたと宣言する人間を近付けるわけがない。さっさと交代させるに限る。
そこまで考えて、はたと気が付いた。デリアを排除しても、神殿長側から代わりの側仕えが来るだけに違いない。隠し事が上手いタイプよりは、わかりやすく自己顕示してくれるデリアの方がわたしにとって安全かもしれない。
考え込むわたしにデリアがビシッと人差指を突きつけてきた。
「青の衣なんて着ていたって、あんたなんか怖くないわよ! あたしは神殿長に認めてもらって、そのうち愛人になるんだから!」
わたしが聞き間違えたのか、それとも、ここ最近は幼女の愛人契約が流行っているのだろうか。フリーダの口から聞いた時の衝撃を同時に思い出し、神殿長の年を考えて気持ち悪くなった。
まさか神殿長がロリコンの変態だったとは予想外だ。以前に見た灰色巫女から、秘書系の色気姉さんが好みだと思っていたのに、裏切られた。
「……あの、愛人って、威張ること?」
「そうよ、愛人なのよ? 愛人は女が一番望む地位じゃない。あんた、そんなことも知らないの? まぁ、あたしくらい可愛くないと望んでも無駄だけどね」
「え? 一番望むのが愛人なの?」
これは明らかに常識が違う。少なくとも、フリーダは愛人という立場がどういうものか、わたしと同じような意味合いで理解していた。少なくとも、誇らしそうに胸を張って、威張って、それを目指すとは言っていなかった。
感覚が違うことをすぐに受け入れられないわたしをバカにするように、ギルがニヤニヤ嫌な笑顔で笑いながら肩を竦める。
「当たり前だろ? 青色神官の愛人になったら、灰色神官を逆に使える立場になるんだぜ? 神殿長の愛人なら他の神官もうるさくないだろうし、女は得だよな。……それにしても、お前、ホント頭大丈夫か? こんな常識、なんで知らないんだよ?」
無知だと蔑まれても、怒りがちっとも湧いてこない。むしろ、孤児院の女の子にとっては一番の出世が権力者の愛人だなんて、そんなこと知りたくなかった。
愛人が一番なんて、わたしが今まで接することがなかった常識だけれど、彼らはその中で生きていて、神殿ではこれが常識なのだ。ここで生活圏の違うわたしが何を言っても、受け入れられることはないだろう。
「ギル、言葉が過ぎる!」
頭を抱えたわたしを見て、フランが声を上げた。しかし、ギルはちっとも悪びれることなく、へへん、とわたしを嘲る。
「そいつが物知らずなのが悪いんだよ。誰でも知ってることだぞ?」
「……マイン様、先程神官長もおっしゃったでしょう。態度がすぎる時は諫めるように、と」
「そうだね。ところで、図書室はまだ?」
すごいどうでもよくなった。ギルやデリアを諫めるとか、叱るとか、そんな体力も気力もいることしたくない。
神官長に心酔していて、多分わたしに仕えるのは嬉しくないフランに、神殿長の愛人を目指して、嫌がらせをするつもり満々のデリアと、最初から仕える気も言うことを聞く気もないとわたしをバカにしているギル。
こんな側仕えと何とか上手くやっていく方法を考えるより、本を読めることを考えた方がよっぽどいい。
「神官長に報告しますよ」
「どうぞ」
溜息を吐いたフランが一つの扉を開けて、中に入っていく。
開かれた先にある楽園を目にして、ドクンと心臓が高鳴った。わたしはまた阻まれないか心配でドキドキしながら腕を伸ばして、透明な壁がないが探りながら図書室に向かって足を進める。以前と違い、阻まれることなく中に入ることができた。
「うわぁ!」
完全に中へと入った瞬間、空気が明らかに変わった。
感動に打ち震えながら、わたしは埃っぽい書庫独特の空気を胸一杯に吸い込む。自分が知っている書庫の匂いと違うのは、羊皮紙が主流であることと、木札の存在が多いせいだろうか。インクの質が違うせいだろうか。
それでも、インクの匂いや古い紙の匂いが懐かしくて、嬉しくて、目の奥が熱くなってくる。
図書室の本棚の数はそれほど多くなく、扉の締められた本棚や木札や紙きれが詰まった本棚もある。巻物を保管するための本棚も別にあり、手芸屋で棚に詰め込まれた布のロールのように巻かれた書物が棚に積まれて、タイトルを書いたラベルが垂れ下がっていた。
少し奥には巻物を保管するための円柱型の樽のような箱もあり、納められている巻物のシリーズ名を書いたラベルが貼られている。
等間隔に作られた窓からはさんさんと日が差し込んで明るく、丁度窓の明かりが取れる場所に大学にあるような長机が置かれていた。天板が斜めになっている書見台には上を鎖で繋がれた本が数冊立てかけられて、読んでほしいとわたしに訴えかけてくる。
「これが聖典です」
フランに促され、わたしは鎖に繋がれた聖典を読むために、皮で装丁された表紙にそっと触れた。そして、小口が開かないように止められている皮のベルトを外す。
次の瞬間、小口がぶわりと広がって、表紙が勝手に持ちあがる。湿気を含んだ羊皮紙なら当たり前のことだが、わたしには本が読むことを催促しているように見えた。
あぁ、一体いつぶりの本だろう。
表紙を開くと、ジャラリと重たい鎖の音がシンとした図書室に響いた。少し黄ばんでいるように見えるページをめくる指先が震える。
少し癖のある手書きの文字をなぞりながら、わたしは本を読み始めた。
「おい、昼だぞ。昼食の時間だ」
久し振りの至福の時間に浸っているというのに、邪魔者が現れた。声だけなら耳に入ることもないけれど、わざわざわたしの肩を揺さぶられたら、さすがに現実に戻らざるをえない。
「ギル、図書室は私語厳禁。静かにできないなら、出てってくれる? わたし、本を読むから」
「ハァ!? 昼食だぞ!?」
ギルがぎょっとしたように叫ぶが、わたしにとっては、昼ご飯と本なんて比べる対象にもなりはしない。本を読んでいられたら、二日くらいは食べなくても空腹なんて感じずにいられる。
「わたし、主じゃないみたいだし、ギルがここにいる必要ないよ? 勝手に食べてきていいから、出てって」
「お前……」
人が親切に自由を与えてあげているのに、ギルはぎょっとしたように目を見開いて、まだ何か言おうとした。
「邪魔、しないで」
理性が切れる前に、意識的に魔力の蓋を開いて、全身に魔力を行き渡らせる。先程の奉納で何となく掴んだ魔力の放出を早速使ってみた。
次の瞬間、フランがギルとデリアの首根っこを引っ掴んで、慌てた様子で図書室を飛び出していく。
うん、静かになった。
魔力を中心に押し込めて、わたしはまた文字列を追っていく。
4の鐘が鳴って、ルッツが来るまで邪魔は入らなかった。