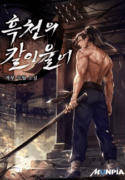Ascendence of a Bookworm: I'll Stop at Nothing to Become a Librarian RAW novel - Chapter (99)
祭りの後
「バカ! 届いてねぇよ!」
ルッツがぎょっと目を見張ったとおり、わたしが投げたタウの実は土の部分に届かず、ギリギリ石畳の隅に叩きつけられ、パン! パパパン! と弾けた。
赤い実が割れた瞬間、小さい種が辺りに広く飛び散って、いきなり何本もの芽がむくむくっと顔を出し始める。土の部分に飛んだ種は芽を出し始めたが、石畳の上に落ちたものは急速に枯れて行き、発芽した物はあっという間に足首辺りまで成長してきた。
「うわっ!」
「わわっ!?」
「これはすぐに成長する。膝くらいになったら次々と刈っていくんだ!」
腰が引けている孤児達に指示を出しながら、ルッツがにょきにょきと成長していくトロンベをきつい眼差しで見据える。
「フラン、マインを回収して後ろの方で待機!」
ルッツの指示と同時にわたしはフランに抱き上げられて戦線離脱だ。刃物を全く持っていないわたしにできることはみんなの応援くらいだ。
「みんな、頑張れー!」
「かかれ!」
ルッツは鉈のような刃物を握って、一番奥の方へと飛び散った物を刈りに走った。ルッツに続いて走り、一番にトロンベを刈ったのはギルだ。
「ていっ!」
ギルが持っている刃物がブチッという音と共に、細い枝を切る。無造作な切り方でも枝が簡単に切り落とせたことと、切られた枝がそれ以上は成長しない様子を見た孤児院の子供達が一斉にトロンベに切りかかった。
「マイン様、これは何でしょうか?」
フランから神官長にどれだけ情報が流れるだろうか。これはもしかしたら、お説教フラグだろうか。大騒ぎではなく、神殿の外ではよくあることとして何とか誤魔化せないかな、と必死で頭を回転させる。
「高級紙の材料です。これでいつもの紙よりずっと高価な物ができますね」
嘘は言っていない。でも、フランが聞きたい答えではないはずだ。フランが何か言いたげに口を開くと同時にギルの声が響いた。
「そこまで成長するとナイフじゃ無理だ。退け! オレがやる!」
わたしがバッと振り返ると、ギルがナイフを持った女の子を下がらせて、自分達の太股辺りの高さに伸びた枝を刃物でザンザンと切り落としているのが見えた。嬉々として森に行っているギルの成長が目に見える。
「よっしゃ! やったぜ!」
ガッツポーズしたギルがこちらを向いて、ニカッと得意そうな笑みを見せた。これは後で褒めろ、というアピールだな、と理解して、軽く頷いておいた。
「……もう残ってないな?」
ルッツの言葉に周りを見回していた子供達が大きく頷いた。
「どうする、ルッツ? これ、いくつか置いておいて、また成長させる?」
せっかくの高級素材が比較的安全に刈れるのだから、この機会を逃すのはもったいない、とわたしが提案すると、ルッツは頭を横に振った。
「あと一つか二つ分だけ刈ったら、あとは予定通り投げ合いっこにしようぜ。土から離したタウの実はカラカラに干からびて枯れるし、まだ森を探せばあるだろうから、取りに行けばいい」
「みんな、悪いけれど、もうちょっと刈ってもらっても良いかしら? これで作った紙はとても高級なものになるの。孤児院に回せる費用が増やせるわ」
「マイン様、費用が増えたらどうなるんですか?」
お金に関しては全くと言っていいほど、知識がない子供達が不思議そうな顔をする。彼らにとって生活に必要な物は全て神の恵みだ。
世の中、何をするにもお金がかかるということも、孤児院で作っているスープの代金も、実はまだ子供達が自分達で賄えているわけではないということも説明はしたが、理解できていないだろう。
「費用が増えたら、自分達で作れるご飯が増えます。それから、冬の薪が孤児院のために買えるようになります」
「よし、やろう!」
孤児院の薪の割り当てはそれほど多くなく、暖炉があるのが女子棟は食堂だけで、男子棟は大部屋一つだけ。そして、薪が切れたら、石造りの建物は一気に冷たくなるので、日中も団子のように固まっているようになるらしい。
金銭的に切り詰めなければならない環境で、冬の食料と暖房は切実な課題である。
子供達がやる気になったので、そのあと3個分のトロンベを刈り取った。トロンベの枝だけで籠がいっぱいになったし、なるべく早く皮に加工しなければならないので、トロンベ狩りは終了となった。
「じゃあ、残りのタウの実をぶつけ合って遊ぶか?」
ルッツの提案に、意欲的にトロンベを刈っていた子供達が目を瞬いて首を傾げる。
「えぇ? 残りも全部紙にしなくて良いの?」
「ぶつけて遊んでなくなったら、また拾いに行けばいいさ。今日みたいに」
ルッツの言葉に子供達は歓声を上げた。今日のタウの実拾いが相当楽しかったようだ。羨ましい。
何回もトロンベが芽を出したせいで、雑草が枯れて掘り返されたようにぼこぼこになった土をある程度均し、ちょっと浮いた石畳を上から踏みつけて元通りにした。
「この辺り、雑草が完全になくなっているけれど、それはどうしようもないよね?」
「そうだな。でも、この季節ならすぐに草なんて生えてくるさ」
「……除草の手間が省けたと前向きに考えるようにいたしましょう」
星結びの儀式が終わったところだし、こんな裏側を見に来るような青色神官はいないので、特に問題はないだろうと結論付けた。
「オレはタウの投げ合いを仕切ってやるから、マインは着替えて来い。顔色が悪い。そろそろ熱が出るぞ」
「うん、確かに身体がだるくなってきたかも。寒気がする」
「デリアが風呂を準備しているはずですから、すぐに身体を温めましょう」
フランがそう言ってわたしを抱き上げた。スタスタと歩くフランの肩越しにタウの投げ合いを始めた子供達の様子が見えた。二手に分かれて、きゃあきゃあと歓声を上げながら、タウの実を投げ合っている姿は、下町の子供達と全く変わらない。孤児院にもう少し娯楽を取りこんであげたいと思う。
「もー! 何をしてるんですの!? 孤児と遊んで体調を崩すなんて、青色巫女のすることではありませんわよ!」
でろんとフランにもたれかかって部屋に戻ると、目を三角にしたデリアがいた。風呂場までフランに連れて行ってもらった後は、フランを追い出したデリアが生乾きの服を剥ぎ取って、準備されていた湯船の中へ放り込まれる。
少し温めだったお湯に熱いお湯を足してもらって、丁度良い温度に調節してもらった。「ずいぶん熱いお湯がお好みなのですね」とデリアが小さく呟いた後、キッとわたしを睨む。
「身体が冷え切っているから熱いお湯が欲しくなるんですわ! 身体が弱いなら、水遊びなんてするものではありません。それくらいご存じでしょうに! もー!」
「……デリア、ちょっと静かにして。せっかくいいお湯なんだから」
温かいお湯で全身を温められる環境にホッと息を吐く。
「あたしが準備したんだから当然ですわ」
「えぇ、デリアの言うとおり。デリアのお陰でとても心地良いわ。ありがとう」
わたしは未だに井戸で水を汲むことができないので、一人でお風呂を準備するなんてできないのだ。
「言われたことをしただけですもの。ギルじゃあるまいし、仕事に感謝の言葉なんて……」
ブツブツ言っているが、照れているだけだとわかっている。
クスと小さく笑いを漏らした後は、肩までお湯につかって、わたしはトロンベの事を考えた。
以前はほとんど発芽寸前だったせいだろうか、それとも、わたしが魔力や身食いに関する知識が全くなかったせいで意識されなかったのか、魔力の流れはほとんど感じなかった。
今回はハッキリとタウの実に向かって魔力が流れて行くのを感じた。水風船状態のタウの実を発芽させるには、奉納で小魔石2~3個分くらいの魔力が必要だと思う。
身食いが持っている魔力の量にもよるが、タウの実を使えば、身食いで死ぬ子供は減ると思う。まず、身食いという病気が周知されることが大事だし、必ずトロンベが発生するので、刈りとれるだけの人数が周囲にいることが必要な条件になる。
ついでに、刈り取った枝はマイン工房が引き取れればありがたいなぁ、と皮算用してみた。
ただ、ルッツが言っていたことが事実ならば、タウの実は保存できないようだ。土から離すと春なら半日ほどで水がなくなってカラカラになり、水分たっぷりになった夏の実でも一日二日でカラカラに乾燥してしまうらしい。石畳に落ちた種が発芽することなく急速に枯れてしまったように。
トロンベが育っていくのと同じように土の上に置いておけば、いきなり枯れはしないと思うが、風や雨でどこかに流されて、秋に突然街中でトロンベが発生するのも怖い。
「……とりあえずベンノさんに報告かな?」
春から秋の初めまではトロンベを自分の意思で採集可能になったことを報告して、トロンベに関する情報収集と身食いに対するタウの実の使い方の情報拡散をお願いしてみよう。
思考が一段落したので、ざっとお風呂から上がった。次の瞬間、頭がくらりとした。熱が出たのか、のぼせたのかわからない。
頭を押さえてその場にペタンと座り込むと、デリアが悲鳴を上げかけた口を押さえて、手早くわたしの全身を拭い始めた。ところどころ拭いきれてないままにブラウスとスカートを着せると、バタバタとフランを呼びに行く。
「マイン様!」
「……あ~、寝台に布団入れなきゃダメだったね。板の上でいいから寝かせて」
フランが抱き上げたまま、板が剥き出しの寝台に寝かせるべきかどうかで右往左往しているのを見て、そう言うとフランは丁寧に寝かせてくれた。
「デリア、ルッツを呼んできて。フランは外に出られるように着替えてくれるかしら? 早目に帰った方が良さそう……」
「かしこまりました」
子供達と一緒にタウの投げ合いをしていたルッツは当然ぐしょ濡れなので、わたしはフランに抱き上げられて帰宅した。
祭りで集中砲火を食らって神殿で服を着替えた、というルッツの説明に母はやっぱりね、と溜息を吐いた。側仕え失格だと深刻な顔で謝るフランには「マインを星祭りになんて出したら、こうなることはわかっていたわ。数日間は寝込むから、神官長によろしく伝えてくださいね」と軽く言って、わたしをベッドに放り込む。
「ずぶ濡れになったお祭りは楽しかったの?」
「……うん。ビックリすることがいっぱいあったけど、孤児院の子達もみんな笑ってた。よかったよ」
ルッツや家族の見立ては正しく、わたしは結局熱を出して三日間寝込んだ。見舞いに来てくれるルッツにタウの実やトロンベについての報告をベンノに頼むと、「詳しいことを話し合いたいから、熱が下がったら神殿に行く前に店に来い」という返事が返ってきた。
「ベンノさん、おはようございます」
「また面倒を起こしやがったな」
いきなり不機嫌そのものの赤褐色の目でじろりと睨まれて、わたしはうっと怯んだ。
「……め、面倒って、いつどこに出るのかわからなかったトロンベの出現するのを待つことなく、採れるようになったんですよ? 最初から人数を揃えておけば、簡単に全部刈りとれるから安全だし、褒められることじゃないですか?」
「それに関しては、確かに。タウの実がトロンベの種だと判明して、トロンベが安定供給できるようになるのは喜ばしい。だが、付随してくる面倒の方が多いだろう?」
「そうなんですか?」
付随してくる面倒に関して、全く思考が向いていなかったわたしに、ベンノは「やっぱり考え無しか」と呟くと、わたしの隣に立っていたルッツに視線を向ける。
「ルッツ、悪いが、マインの到着が遅れることを神殿に知らせてきてくれ。その後は呼ぶまでマルクについていろ。お説教には時間がかかるからな」
「はい、旦那様」
ルッツが苦笑して、「頑張れよ、マイン」と慰めにもならない激励の言葉を残して退室していく。
味方がいなくなった部屋の中、ベンノがトントンと軽く指先で机の上を叩いた。
「ルッツから聞いた。タウの実が魔力を吸い取って一気に成長してトロンベになったと。間違いはないか?」
「ないです」
「魔術具の代わりにはなりそうか?」
冬の間、タウの実が手に入らないことが不安要素だけれど、わたしの場合、タウの実が20個くらいあれば、次の春まで魔力が溢れて死ぬことはないと思う。身体が成長すれば魔力量も増えるらしいので、成人する頃にはいくつくらい必要になるかわからない。
「……なると思います。だから……」
「それ、絶対に漏らすな」
「え?」
厳しい表情でベンノが言った。身食いを助けるために、タウの実の使うことについて情報の拡散をお願いしていたわたしは、ベンノの言葉が信じられなくて、大きく目を見張った。
「魔力の管理は貴族の管轄だ。森で簡単に拾える実が高価な魔術具の代わりになると知れば、貴族社会や神殿の在り方がひっくり返る恐れがある。変な伝わり方をしたら、多分、お前が潰される」
「……でも、黙っていたら、平民の身食いはずっと助からないままですよ?」
せっかくお金をかけなくても、助かる方法が見つかったのに、知らせることができなければ助かる者も助からない。
「あぁ、そうだな。だが、身食いの子供をどうやって選別する? 俺にはわからないが、身食い同士なら、傍から見てわかるのか?」
ふるりと頭を振った。わたしが会ったことがある身食いはフリーダだけだが、見ただけでフリーダが身食いだとか、魔力を持っているなんてわからなかった。誰が身食いかわからなければ助けられるはずもない。
「生まれた子供全員にその実を握らせて、魔力を持っているかどうか識別することは可能かもしれない。だが、魔力持ちだとわかった時点で貴族に取り上げられるだろう。判別と同時に取り上げられると分かれば、誰が識別させようとする? 少なくともお前の家族は連れて行かないだろう?」
ぐっと言葉に詰まった。家族と離れたくないわたしは魔術具に頼らないで延命する術が欲しいと思っていた。それは貴族を避けるためだ。大々的に識別すれば、それは貴族の知るところになるだろう。それでは意味がない。
そして、大々的に周知するのでなければ、身食いに関することもタウの実で助かることに関しても情報が伝わるわけがない。
「生まれてすぐの子供を大々的に集めるのでなければ、熱を出した子供を連れて来いというのか? 身食いならばタウの実で治るが、他の病気なら、残念でした、と追い返すのか? そんな判別をしていたら、逆に妙な病気をもらうし、治せなかった親からは無駄な憎しみを買う」
あの子の病気は簡単に治したのに、どうしてウチの子は、と言われるのは目に見えている。わたしは自分では考えられなかったベンノの予想図にギュッと拳を握った。
「それに、貴族を頼らず身食いが成長することで、周囲が困ることになる可能性は全くないのか? 大きな魔力を持って、知識なく育った身食いが正しく魔力を扱うことができるのか? 魔術具を買うことができない貴族の子供を預かって魔力を集めることで、神具を動かしていた神殿の在り様はどう変わる? 魔力を独占している貴族社会自体が揺らぐことにはならないのか?」
「……わかりません」
立て続けに並べられたどの疑問にもわたしは明確な答えを返すことはできなかった。社会情勢、政治の仕組み、この世界における魔力の扱いさえ、わたしは知らない。
「どれだけいるのかわからない身食いを助けるためとしては、あまりにも余波が大きすぎる。とりあえず、今はお前が神殿から追い出されたり、魔術具を命の盾として脅されたりする状況になったりしても、こっそり生きていける手段を得たと思って、黙っていろ。事が大きくなりすぎている。少なくとも俺の手には負えん」
ベンノの手に負えないことが、わたしの手に負えるわけがない。中央での粛清が終わって、貴族の大規模な配置変換が終わって、貴族が少ないながらも情勢が落ち着いてきた矢先に混乱を撒き散らしたいのか、と問われれば、答えはノーだ。そんな面倒な事はしたくない。
「森でトロンベを採るくらいなら、今までと同じだから誤魔化しも効くだろうが、身食いの判別や延命については黙っていた方が良いと俺は思う」
「……はい」
わかっていても助けられるはずの命が助けられないことに、不満が残る。わたしの表情に不満がハッキリと出ていたのだろう、ベンノが困ったように肩を竦めた。
「そんな顔をするな。……お前の目に映る範囲内に身食いがいて、こっそり助けられるなら助ければいい。それを貴族に感付かれるなと言っているだけだ。お前は貴族社会に宣戦布告できるのか? 本を作った時の顧客は基本的に貴族だぞ?」
ベンノの言葉の最後にわたしはちょっとだけ笑った。笑ったことで、ほんの少し気分が浮上した。苦しんでいる身食いが目の前にいれば、助ける。見えないところまでは関知しない。今までどおりのスタンスで行けばいい。
「せめて、一般市民が気軽に本を読めるようになるくらい識字率が上がってからじゃないと宣戦布告なんてできませんね。そんな面倒なこと、する気もないですけど」
わたしがベンノの軽口に乗ると、ベンノもフッと表情を緩めた。
「まぁ、確かに一般市民が本を読めるようにするのは面倒だな」
「面倒なのはそっちじゃなくて、宣戦布告ですよ。本を普及させたいんですから、識字率を上げる計画は当然ありますって」
せっかく神殿にいるのだ。いずれ孤児院を利用して、寺子屋ならぬ神殿教室を開催するつもりだ。手始めに孤児達への教育をする過程で、灰色神官を教師役に育てあげる。そして、わたしにわかる範囲で印刷技術を開発して、聖典を元にした教科書を作る。聖典を印刷して布教するのであれば、神官長も文句は言わないはずだ。
「どうです、完璧でしょう?」
うふふん、とわたしが胸を張ると、ベンノは何故か頭を抱えてしまった。
「お前の計画だから穴だらけだとは思うが、それはいい。……なぁ、マイン。お前、本以外の事に頭を使えないのか?」
「はい、多分」
本以外の事に使ったことがないので、使えるかどうかわからないというのが一番正しいけれど、と付け加えたら、ベンノは「残念すぎる」と、深い、深い溜息を吐いた。
失礼な! とむくれるわたしに「事実だ」と笑っていたベンノがスッと表情を変える。真剣な表情で、心もち声を潜めるのは、真面目な話がある時だ。
「トロンベをなるべく独占できるようにタウの実については黙秘ということでいいな?」
「はい」
「では、先日渡した課題一覧の最後の項目について、お前の意見が聞きたい」
……あぁ、そのためにルッツを使いに出したのか。
お説教のためと言いながら、ルッツを外に出した意図がわかって、わたしはコクリと唾を呑みながら、ベンノを見つめた。