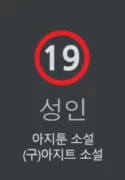Kanna no Kanna RAW novel - chapter (124)
第百十四話 足を揃えてみんなが踏み出す中、一人だけ逆走している心境。
「浅手を負わせて手痛い反撃されるよりはマシだろう。……お嬢様」
ランドは守護対象に向けて言った。
「私は大丈夫。それより、状況の確認を急ぎましょう」
突発した状況に動揺を見せるも、ファイマは己に左胸に手を添えて逸る鼓動を納めている。今回だけではなく、既に何度か襲撃を受けている身。顔色は悪いが落ち着きを取り戻し始めていた。
「早く逃げようよ……」
マリトが父親の影から震えた声を発した。いつ泣き出してもおかしくない様子だ。パペトもそんな息子を抱き寄せつつも、青ざめた表情は変わらない。
「た、確か遺跡の周辺には騎士団の方々が待機していた筈ですよね。か、彼らたちは無事なのでしょうか。……まさか、今襲ってきた奴らに──」
「いえ、それは無いと思います。我ら幻竜騎士団の人間は団長の指導のもと、ありとあらゆる状況を想定して訓練されています。その中には対暗殺者との戦闘や奇襲された状況下での突発戦も含まれています。先ほど襲ってきた者たちの動きを見る限り、そう易々と遅れをとる筈はありません」
カクルドが自信を持って断言すると、ファイマの顔が少し引きつる。
「ど、どんな訓練内容だったのか、少し気になるわね」
「それはもう……過酷でしたね」
カクルドとスケリアの目からスッと光が失われ、乾いた笑みが零れた。
「野営訓練中に、団長を含む部隊長クラスの人たちが突然襲いかかってきたりしましたから。しかも、皆の気が緩んだ頃を見計らって抜き打ちで行うんです。我々の対処が甘かったりすると、団長が直々に訓練メニューを追加してきますから、皆が必死ですよ」
団長
なにやってんの!?
ツッコミを入れたくなる衝動を押さえ込んでいると、パペトが更に口を開く。
「で、ですが現に我々は襲われましたよ?」
「……あれだけの人数の目を掻い潜ったとも、たった三人を相手に全滅したとも考え難い。とすると、三人を見逃してしまうほどの何かが起こっていると見るのが妥当だな」
アガットの見解にランドは頷くとすぐに指示を出した。
「
不審者
の正体は気になるが、まずは外の者たちと合流する方が先決だろう。もし異常事態に直面していたならば、彼らだけでは対処できていない可能性が大きい。ならば、共同で事にあたる必要がある」
ランドがおそらくこの状況下で下せる最善の指示を下しただろう。俺を除くその場にいるすべての人間が納得した様子を見せていた。
「あ、ちょっと待ってくれ」
動き出そうとする全員の足を、ほかならぬ俺が制止した。
「ってカンナ氏!? ここで妙なボケを突っ込まないで欲しいでござるよ!」
「
クロエ
、本当にイイ感じに遠慮が無くなってきたな……」
コメカミが
痙攣
するがどうにか堪え、俺は不審者の亡骸に近寄った。
「お、お兄さん! なにやってるの! 急いで外の人たちを助けに行かないと!」
マリト少年が俺の腕を掴み、出口の方へと引っ張った。慌てて掴んだ拍子に爪が刺さったのか、腕にチクリと痛みが走る。だが俺は彼の手を振り払うと遺体に近づく。遺体の傍にしゃがみ、その胸元に手を触れた。
この不審者たちの姿を見たときから感じていた予感が、確信に至った俺は討伐した魔獣を解体するためのナイフを取り出し、彼らの衣服を切り裂いた。
「おい貴様、そんなことをしている場合では──ッッ!?」
声に苛立ちを含ませたアガットが俺の肩を掴むが、露わになった不審者の胸元を目にした瞬間にその表情が驚愕に変化した。
「これは……渓谷で襲ってきた奴らと同じ──ッ!?」
そうなのだ。以前にフレイムリザードの渓谷で襲いかかってきた者たちと同じように、この遺体の胸元には宝石が埋め込まれていたのだ。
先に言っておくが、俺にだって確証があったわけではない。こいつらが襲ってくる光景に、渓谷での一件が頭の片隅でチラついただけだなのだ。あくまで『念のため』という気持ちが大きかった。だが、今回はその『念のため』が大正解だったようだ。
「……これが、拙者に埋め込まれていたのでござるか」
クロエは複雑な感情を顔に浮かべ、服の上から己の胸元に刻まれた傷跡に触れた。彼女は以前、何者かにこの遺体と同じ類の宝石を埋め込まれ、操られていたのだ。
ファイマは険しい表情で遺体に近づき、指先で宝石に触れて目を閉じる。
「案の定、同じ人間が手がけた術式が施されているわ」
「そういうのって分かるものなのか?」
「複雑であればあるほど、施した人間の好みや癖が出てくるのよ。自意識の封印、行動の操作、自死の仕組み等々、趣味の悪い術式のオンパレードよ。ただ──」
宝石から手を離したファイマは、苦虫を磨り潰したように顔を歪めた。
「分野は違うし認めたくもないのだけれど。これだけは断言できる。この宝石に術式を施した人間は、間違いなく一流の魔術師よ」
非人道的な行いでありつつも、ファイマは未だ顔の知れない魔術師の腕を称賛した。人としては相容れないながらも、魔術師としてその腕を認めたのだ。
「……自分から引き止めておいてあれだが、急いだ方がいいかもしれないな」
こうなると、外の状況がいよいよ心配になってくる。
「渓谷での襲撃と今の状況は、少なからずの繋がりを持っている。この事実が分かっただけでも大きいわ。気を引き締めていきましょう」
ファイマの言葉に、全員が頷いた。
周囲を警戒しながら、俺たちは遺跡の出入り口へ急いだ。幸いにも建物の内部で新たな襲撃が来ることはなく、スムーズに出入り口にたどり着くことができた。
残念ながら、襲撃者達の遺体は中に放置したまま。さすがに人間二人分の体は荷物に他ならない。ただ、念のため、ガッチガチに固めた氷の棺を用意しその中に遺体を納めておいた。死体そのものを氷漬けにしなかったのは、以前に読んだSF小説で冷凍された人間は体細胞が破壊される云々と書かれていたのをうっすらと覚えていたからだ。詳しいことは知らん。
問題なく遺跡から出られた俺たちの前に広がっていたのは、予想通りの光景だ。
騎士団の面々が襲撃を受けているのはなんとなく想像していた。 ただそれが、人間ではなく魔獣の集団であったのだけは予想外であった。
魔獣の集団には四速歩行の獣型魔獣もいれば、ゴブリンやオーガといった人型の魔獣もおり、統一性が無かったがその数は〝沢山〟と表現するしかないほどだ。
外で待機していた騎士達は全員が抜刀し、迫り来る脅威と対峙していた。天竜騎士団の人間も飛竜に騎乗して魔獣を蹴散らしている。パッと見で、深手を負っているような者はいないようだ。カクルドの言う通り、一人一人が手練れであるのは間違いないよだ。ただ、相手をする数が多すぎて持ち場を離れられない状況だ。
「竜騎兵はなんで空を飛んでいないのでござるか?」
天竜騎士団の者達は飛竜に乗ってはいたが、空を飛ばずに地面に足をつけたまま戦っていた。それだけでも十分に強いだろうが、竜騎兵の持ち味は空を飛べることだ。上空からの一撃離脱による機動力、強襲力が最大の武器であり、あえて地上で戦う利点はないはずだ。
「実際に聞いてみりゃぁ分かるさ」
俺は再度、氷の槌を具現化。懐から氷爆弾の玉を取り出すと氷砲弾の形に形成した。
「名付けて、
氷結榴弾
──かっ飛べやぁ!」
幻竜騎士団の一人に、死角から襲いかかろうとする魔獣に向け、俺は冷気を満載した砲弾を放った。