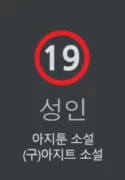Kanna no Kanna RAW novel - chapter (137)
第百二十七話 断ち切る雷光
──パキンッ。
ガラス細工が割れるような音がクロエの懐から響いた。
カンナから渡された
、氷結晶だ。
──仕込みの初めは、作戦を話し合っていた終わり際。
カンナはラケシスを正面に、ファイマたちに背を向けた時だ。
『二人とも、聞いてくれ』
口元に手を当てたカンナは小さな声で呟いた。
咄嗟に反応しそうになる二人に対して、カンナは更に言葉を重ねる。
『おっと、そのまま動かないでくれ。今はちょいと
細工
をして、あいつに俺の声が届かないようにしてるけど、視覚はそのまんまだからな』
ファイマが使用していた遠話の魔術式を切っ掛けに、カンナは自分でも今まで完全に忘れていた氷の精霊術の特殊な使い方を思い出していた。
すなわち、空気分子の動きを冷気断層によって極限にまで抑え、分子振動による音声の伝達を制限する術である。
『あんまり使い慣れてない術だから長時間は続けられないし奴に悟られる恐れがある。だから手短に段取りを説明するぞ。まずはクロエに──』
「──ファイマ殿」
「良いわ、こっちの準備はできてる。あの
クソ野郎
に、一発お見舞いしてきて!」
「承知!」
クロエは全身に魔力を漲らせ、大地を蹴った。
──まず最初に、カンナは二つの氷結晶を取り出し、クロエに手渡した。もちろん、ラケシスからは見えないよう、慎重にだ。
『そいつの片割れが砕けたら合図だ。そしたらクロエ、お前は何がなんでも
ラケシス
のところまでたどり着け。あの糸の正面から突破できる可能性があるのは、お前の『雷刃』だけだ』
カンナの中で、それは希望的観測ではなく、ある程度の根拠があった。
それはファイマが最初にはなった魔術式──風の刃がラケシスの糸を〝弾いた〟のに対し、クロエの『雷刃』は〝断ち切った〟っていたのだ。
そして、確信を持てたのはラケシスがクロエに攻撃を仕掛けた瞬間。あの時、彼女は間違いなくカンナのみを案じて声を発してしまっていた。だが、ファイマを守るため、その場を動く素振りは無かった。だというのに、ラケシスはクロエの足を止めようとするかのように攻撃を仕掛けた。
──ラケシスはクロエに警戒心を抱いている。
内心を悟らせないように、ラケシスはクロエに対して挑発的な態度をとった。だが、カンナはラケシスが見せたほんの僅かばかりの動揺を見逃さなかった。
カンナの恐ろしい点は、誰もが見逃すほんの僅かな違和感を的確に見抜く直感力。そして、絶望的な戦いの中であってさえ微塵も諦めない、不屈の精神が生み出す勝利への執念。
確信を抱いたカンナはラケシスの意識を己に集め、その瞬間を最大の好機と定めたのだ。
クロエが駆け出すのとほぼ同時に、カンナが糸の乱撃に飲み込まれる。
カンナは氷壁を具現化するが、その表面は見る見る内に削り取られていく。
だが、カンナの合図から少し遅れて、ラケシスがようやくクロエの動きに気がついた。驚いた様子を見せるラケシスに、カンナは会心の笑みを浮かべる。
「小癪な真似を!」
ラケシスは力任せに糸を振るい、カンナを吹き飛ばした。
だが、躯が宙を舞う中、カンナの紅の瞳がクロエを射抜いた。
──やれ、クロエ!
言葉無くともそう命じられたように思えて、クロエは胸の奥が高鳴った。あえて『これ』を言葉で表現するのならば『歓喜』だ。
「御意に、カンナ様……!」
四肢にこれまでになく力が漲るのを感じながら、クロエは疾駆する。
「舐めないで欲しいですね。あなた程度をつぶす手段などいくらでもあるんです」
ラケシスは魔力を高ぶらせ、糸の本数を大きく増やす。増大した魔力の糸は生き物のように動くと、束ねて織り込まれ、やがて巨大な『大蛇』を形作った。
「封糸演舞──第一幕『大蛇の型』。僕の攻撃が単純な糸の攻撃ばかりと思わないことです」
糸で作られた大蛇が、クロエを飲み込まんと大口を開けながら迫る。
「『雷刃』!」
クロエは迷わずに刀に雷光を宿し、一閃する。大蛇は容易く両断され、形を失い元の糸へと戻っていった。その様を確かめる事もせず、クロエは走り抜ける。
「まだまだ行きますよ? 第二幕『怪鳥の型』」
ラケシスが次に糸で形作ったのは巨大な鳥。
「──っ、『雷刃』!」
振るわれた巨大なカギ爪ごと、クロエは怪鳥を切り裂いた。
己の技を容易く迎撃されたことに、ラケシスはさほど危機感を覚えていなかった。
ラケシスの糸は、武器であると同時に触覚としての性質も有していた。糸を通じ、痛覚と視覚以外の感覚を共有できるのだ。そして、断ち切られた糸を通じ、クロエの刀が凄まじい高温を放っている事実に気がついていた。
刀が発する高温は、既に人間が握っていられる限界温度を超えている。
もし仮に、火属性や地属性に適正のある人間であったならば、熱への高い耐性を有していたり、躯そのものの頑強度が優れていたかもしれない。だが、クロエが雷の属性にしか適正がないのは、彼女を一度傀儡としていたラケシス本人が知り得ていた。つまり、雷に対しての高い耐性を有していたとしても、熱に対する耐性は一般人とさほど代わりはない。いくら身体能力が優れている黒狼族であっても限度はある。
クロエはこれ以上、『
雷刃
』を使うことは出来ない。
「無駄な足掻きでしたね。これで終わりです。第三幕『狼牙の型』」
三度目で形作られたのは『大狼』。黒狼族であるクロエに対して向ける最後の攻撃としては皮肉が効き過ぎている。
ラケシスは黒狼が大狼に噛み砕かれる未来を想像し、ふとクロエの手元が目に入った。
クロエの顔は激痛に歪んでいた。ラケシスの想像通り、握っている刀の柄が超高温を発しているのだ。しかし、彼女はそれでも柄から右手を離さない。
──左手には、半透明の球体が握られていた。
ラケシスが疑問を抱くよりも先に、クロエは半透明の球体を右手に握る高温を発する刀の柄に叩きつけた。衝撃で球体が砕けると彼女の周囲に光を乱反射する細かい粒子のような物体が舞った。
そして──クロエは叫ぶ。
「『雷刃』!!」
「────ッッ!?」
もはや使用の限界を超えていたはずの『雷刃』をさらに行使し、クロエは大上段で大狼を叩き斬る。予想外の出来事にラケシスは戦闘が始まってから初めて余裕の表情を崩した。